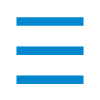中学生時代に運動系の部活動で活躍していた、というカメラマンの皆さんならご存じかと思いますが、ひと昔前の部活動といえば、今では信じられないような根性主義が当たり前でした。
今回は、昭和~平成初期にかけて存在した“今ではちょっとヘン”な部活文化を振り返りながら、現代のスポーツ指導がどのように変わってきたのかを見ていきましょう。
目次
水飲み禁止!? 今ではありえない「根性指導」
かつての部活動では、「練習中に水を飲むのは甘えだ!」という考え方が一般的でした。
脱水症状や熱中症の危険性が知られていなかった時代、「我慢こそが強くなる近道」と信じられていたのです。
しかし今では、科学的にもこまめな水分補給がパフォーマンス維持に不可欠であることが証明されています。
「気合いよりも安全第一」――この意識の変化こそ、現代のスポーツ教育の大きな進歩といえます。
先輩は絶対!? 上下関係のカベ
昔の部活動では、「先輩=神様」的な上下関係が存在していました。
部室に入る順番、座る位置、声のかけ方まで厳しくルール化されていたことも。
先輩が来ると全員で立ち上がる、後輩は荷物持ち担当…そんな「部活ヒエラルキー」を経験した人も多いのではないでしょうか。
もちろん礼儀は大切ですが、恐怖ではなく信頼でつながるチームこそが強い。
近年では「縦より横のつながり」を重視する部活動も増えています。
休む=サボり?「休養=悪」という風潮
昔は「毎日練習してこそ上達する」という考えが根強く、体調不良でも休むことをためらう風潮がありました。
しかし、今のスポーツ科学では「休むことも練習の一部」とされています。
筋肉や心を回復させることで、次のパフォーマンスがより高まる…“休む勇気”を持つことが、ケガの予防やメンタルの安定にもつながるのです。
精神論だけで乗り切る時代
「走り込みで根性を鍛えろ!」
「気合いが足りないから負けた!」
かつての指導現場では、科学的根拠よりも精神論が重視されていました。
しかし、現代のトレーニングはデータと理論に基づいた「スマート練習」へ。GPSや心拍数、栄養管理などを活用し、選手一人ひとりに合わせた指導が主流になっています。
気合いだけでは勝てない…そんな現実を、今の時代はきちんと受け止めています。
文化の変化が「より楽しく続けられる部活」へ
時代とともに、部活動も進化しています。
安全面の配慮、メンタルサポート、個性を尊重する指導など、それらはすべて、「スポーツを楽しむ」ことを目的とした文化の変化です。
「つらくても我慢」が美徳だった時代から、「楽しみながら成長する」時代へ。
この変化こそ、子どもたちの未来にとって何より大きな一歩かもしれません。