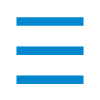不登校の子どもが増加する中で、スポーツがストレス解消やコミュニケーションの場として重要な役割を果たしていると注目されています。
このような状況において、どのような支援が提供されているのでしょうか。
指導者や不登校を経験したアスリートに話を伺いました。
どんな状況の子どもでも、楽しくスポーツができる環境整備は心身の健康のために必要でしょう。
生き生きとしている子どもの笑顔を写真に収めたいですね。
(※2025年2月20日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
目次
スケボーで心の支援。不登校児童へのサポートを強化
新潟駅から車で約30分、秋葉区にある屋内型スケートボードパークでは、昨年12月の夕方、10人ほどの子どもたちが木製の障害物を使ったコースで技を練習していました。
「できた!すごいじゃん!」
スケボー教室「VIVID SKATE SCHOOL」を運営する高橋卓さん(42)が明るく声を掛け、子どもたちは満面の笑みを浮かべています。
2019年に開校したこのスクールには、3歳から50代までの約140人が通っています。
スケボーの技術向上と並行して、不登校児童への支援にも力を入れています。
高橋さんは、20代のころから10年以上にわたり、福祉施設で介護や引きこもりの方々の就労支援を行ってきました。
趣味で始めたスケボーを通じて、悩みを抱える子どもたちを支えられる方法を模索し、「スケボー×福祉」をテーマに教室を開設しました。
スケボー教室で心の支えを得た16歳の若者
「この場所があったから、人とのつながりを維持できました」
そう語るのは、かつて不登校だった16歳の佐藤秀哉さんです。
そのきっかけは、小学2年生の時に同級生の冗談半分の悪口で傷ついたことでした。
徐々に学校に行く回数が減り、最終的に小学5年生からは全く登校できなくなりました。
家にこもり、1日18時間ゲームに没頭し、昼夜逆転の生活を送りながら誰とも会話しない日々が続きました。
そんな時、自宅から車で約15分の場所にスケボー教室がオープンしたことを知り、親に誘われて体験レッスンを受けることになりました。
最初はただ仕方なく通っていたものの、徐々に技ができるようになると、次第に楽しさを感じるようになりました。
スケボーをしている間だけは、漠然とした不安も消え、「無心になれる瞬間」を味わいました。
スケボーは自分のペースで目標を立てられるため、技が成功すると、教えてくれる高橋さんが自分のことのように喜んでくれることが嬉しく感じられました。
また、親と一緒に高橋さんのカウンセリングを受けることもありました。
学校に行けないことへの不安や、生活リズムに関する悩みを話すことで、少しずつ心が軽くなっていったそうです。
あいさつがつなげた心の成長、スケボー教室で見つけた自分の道
このスクールが最も重視しているのは、あいさつです。
「コミュニケーションの第一歩だから」と高橋さんは話します。
佐藤さんも最初はあいさつが苦手でしたが、次第に自分から積極的に声をかけるようになりました。
中学に入学してからは、学校に通う日が徐々に増え、勇気を出してあいさつをすると、クラスメートからも話しかけてもらえるようになりました。
昨年春、通信制高校に入学し、週2回通学しています。
また、ラーメン店でアルバイトも始めました。
母親の真弓さん(48)は、息子の成長を嬉しく感じています。
「このスクールで初めて夢中になれるものに出会い、表情が明るくなった」
と語っています。
高橋さんは、これまでに約10人の不登校児童をサポートしてきました。
「最も大切なことは心の成長です。『自分はこれができた』と感じられることに意味があります。すべての子どもたちに、活き活きとした人生を送ってほしい」
と話しています。
現在、佐藤さんは高橋さんのサポート役として、小学生の指導にも取り組んでいます。
「小さな子どもを教えるのが好きです」
かつて不登校だった自分がこの場所で救われたように、今度はスケボーを通じて子どもたちの成長をサポートしたいという夢を抱いています。
不登校から五輪選手へ!砂間敬太選手の挑戦と成長
不登校を経験し、東京オリンピックに出場したアスリートがいます。
競泳の2021年東京五輪代表選手、砂間敬太さん(29)です。
彼が不登校になったのは、小学4年生の時でした。
特に明確な理由があったわけではなく、学校を休んだ後に「どうして休んだの?」と同級生に聞かれるのが嫌で、次第に学校に行くのが億劫になり、授業についていけなくなりました。
その結果、学校への足が遠のき、3歳から通っていたスイミングスクールにも通えなくなってしまいました。
家にこもる日々が続き、体重は1年で10キロ以上増えました。
「このままだといけないと思いながらも、体が動かせず、もどかしさを感じていました」と彼は振り返ります。
そんな時、手を差し伸べてくれたのがスイミングスクールのコーチでした。
コーチは時折自宅に訪れ、食事に連れて行ってくれました。
その支えがあったおかげで、1年後には再びスクールに通うことができるようになりました。
砂間敬太選手が語る水泳と自己肯定感の成長
学校を休んでいる間、水泳を続けることには少し居心地の悪さを感じていたものの、泳いでいる時だけは不安や迷いが消えました。
体を動かすことで、気持ちが明るくなり、タイムという目に見える成果を通じて自分の成長を実感できました。
小学校6年生の時、初めて全国大会で優勝し、「自分の存在を認めてもらえたような気がした」と振り返ります。
そこで、彼は自分の居場所を感じ、存在意義を見出し、自己肯定感が芽生えました。
中学時代も不登校の生活が続きましたが、天理高(奈良)での寮生活がきっかけで、登校することができるようになりました。
大学を経て、日本のトップスイマーとして成長し、東京オリンピックに出場することができました。
今振り返ると、不登校だった6年間が自分の原点だと感じています。
その時期はただ一日一日を過ごすだけで未来が見えませんでした。
そのため、
「水泳でも大きな目標を見据えるのではなく、目の前の練習を一生懸命頑張ることが大切だと学びました」
と語ります。
最近では、不登校児童が通うフリースクールなどで講演を行うことにも力を入れています。
「学校に通わないことは、私自身も経験しているので否定はしません。ただし、誰かとコミュニケーションを取る場所を持つことは大事です。誰かと話せる場所があれば、気持ちは楽になるものです」
と伝えています。
自分の経験が他の人の役に立つことを願い、これからも発信を続けていくと誓っています。
不登校支援におけるスポーツの役割、卓球とバドミントンの効果
文部科学省の調査によると、2023年度に年間30日以上欠席した「不登校」とされる小中学生の数は34万6482人に達し、過去最高を記録しました。
これで11年連続の増加となり、30万人を超えるのは初めてです。
コロナ禍による生活リズムの乱れなどが原因として挙げられています。
2017年度の調査では、不登校状態にある児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援する教育支援センター(適応指導教室)の約80%で何らかのスポーツ活動が行われていることがわかりました。
この教育支援センターとスポーツの関わりについて研究している神戸親和大学の松田恵示学長(スポーツ社会学)は、不登校の子どもたちを心身の状態に応じて、混乱期、低迷期、回復期に分類し、「特に回復期においてスポーツは非常に有効である」と分析しています。
運動を通じて、コミュニケーションが増え、ポジティブな考え方ができるようになるこの時期に、他者との協働関係を築いたり、ストレスを発散したりする効果が見られるためです。
不登校支援において、スポーツの役割は大きい
松田さんらは2018年に全国の教育支援センターを対象にアンケート調査を行いました。
282の施設から得た回答を基にした論文によると、実施されているスポーツの中で最も多かったのは卓球(87.9%)でした。
次いでバドミントン(78.4%)、バレーボール(28.7%)とネット系のスポーツが続きました。
これらのスポーツは、相手が自分のコートに入り込むことなく、接触も少ないため、ラリーを続ける形で遊ぶことができる点が特徴です。
松田さんは、不登校の子どもたちにどのように大人がスポーツに接するかが大きな影響を与えると考えています。
「楽しみながら遊ぶ感覚で構いません。他者と同じ時間を共有すること自体が、子どもたちにとって非常に価値のある経験になる」と述べています。
一方で、スポーツを強制すべきではないことも強調しています。
「子どもが自発的に意欲を持つまで、待つ姿勢が重要だ」
と松田さんは語っています。