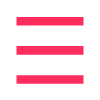日本全体で出生数が減少しています。
2023年に生まれた日本人の子どもは72万7277人で、1899年からの統計で最も少ない数字となりました。
政府や地方自治体は子育て支援の強化を進めていますが、状況の改善にはまだ手応えがありません。
ニッセイ基礎研究所(東京)の天野馨南子・人口動態シニアリサーチャーに、現状を打開するための方法についてお話を伺いました。
あなたはプロポーズする際、子どものことについて話し合っていますか?
妻と夫で子どもを持つことに対する認識は合っていますか?
(※2024年9月7日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
目次
出生率の低下とその誤解・・・天野さんが指摘する地域間の現実
厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の合計特殊出生率は1.20となり、過去最低を記録しました。
特に東京では出生率が1を下回り、0.99となったことで、更なる衝撃をもたらしました。
しかし、天野馨南子さんは「出生率そのものは単純な指標ではない」と警鐘を鳴らしています。
合計特殊出生率は、15歳から49歳の女性が生涯に産む子どもの数を示します。
「夫婦が持つ子どもの数」と誤解されることが多いですが、この計算には未婚女性も含まれます。
そのため、未婚女性の割合が高い地域では出生率が低くなる傾向があります。
例えば、ある地域に既婚と未婚の女性がそれぞれ5人ずつ、計10人いると仮定します。
既婚女性が2人ずつ子どもを持っている場合、その地域の子どもの数は10人で、出生率は1となります。
この地域から未婚女性2人が転出すると、女性の数は8人に減りますが、子どもの数は変わらないため、出生率は1.25に上昇します。
このように、子どもの数が変わらなくても出生率だけが上がることがあります。
天野さんは、こうした現象が全国の地方でも実際に起きていることを指摘しています。
未婚女性は多くが20代前半で都市部に移住するため、過疎地では一時的に出生率が上昇します。その結果、「女性1人あたりの子どもが増えたので少子化対策が成功した」という誤解が広がることがあると警告しています。
出生率だけでなく出生数の増加が少子化対策の鍵!
天野さんが人口減少対策に関与している高知県では、2023年の出生率は1.30と全国平均を上回っています。
しかし、同県の出生数は47都道府県中で2番目に少ない3380人となっています。
「少子化対策で最も重要なのは、赤ちゃんの数を減らさないことです。出生率が高くても、未婚女性が都市部に移住し続ける地域では、子どもの数は増えません。少子化対策の成否を語る際は、出生率ではなく、実際の出生数を基に評価すべきだと考えています」
と天野さんは述べています。
未婚化が少子化の根本原因
少子化の主要な原因は何か、天野さんが指摘するのは「未婚化」です。
1970年と2022年の人口動向を比較すると、第2次ベビーブーム(1971~74年)の前における出生数は約193万人から約77万人に減少し、半世紀で6割の減少を記録しました。
しかし、婚姻数あたりの出生数は1.9から1.5と、2割程度の減少にとどまりました。
大きな変化が見られるのは、結婚したカップルの数です。
1970年には103万件あった婚姻数が、2022年には50万件に減少しました。
「少子化の根本的な要因は未婚割合の増加です。日本は婚外子が少なく、カップルが成立しなければ子どもは生まれません」
と天野さんは強調しています。
さらに天野さんは、「アンコンシャス・バイアス」(無意識の偏見)についても警鐘を鳴らしています。
1990年代まで、男女ともに生涯未婚率は10%未満でした。
つまり、年齢を重ねると誰もが結婚できるという無意識の偏見が根強く存在しており、特に企業経営者や自治体の政策決定者といった高齢層にその傾向が見られると指摘しています。
天野さんは、
「夫婦が持つ子どもの数が減少したために少子化が進んだと考えられがちですが、それは誤りです。エビデンスに基づかず、少子化の原因として婚姻数の減少に気づかないため、この国では有効な対策が取られてこなかった」
と述べています。
若者の結婚意欲は高い。少子化対策の方向性は?
天野さんは、若者の結婚意欲が依然として高いことを指摘しています。
特に興味深いデータとして、東京商工会議所が2023年8月に発表した「東京在勤若者世代の結婚・出産意識調査」が挙げられます。
この調査は18歳から34歳を対象に行われ、既婚者も含めて、結婚に前向きな若者は全体の86.1%に達していることがわかりました。
また、独身者の78.7%が「将来的に結婚するつもりだ」と回答しています。
調査結果では、結婚の障害として、良い出会いがないことや経済的不安(収入や雇用面での心配)を挙げる人が多かったとのことです。
天野さんは、
「日本の少子化の原因は、結婚という出発点が停滞していることにあります。人口減少を食い止めるためにも、行政と企業が協力し、若者をつなげる仕組みや若い男女の雇用の場を増やすなど、まだできることはたくさんあるはずです」
と提案しています。
東京は一極集中の続くが地方は人口減少へ
総務省が発表した2024年1月1日時点の人口動態によると、日本全体の人口は前年比で約86万人減少しましたが、東京都だけは人口が増加しました。
東京への一極集中の傾向は依然として続いています。
過去にさかのぼると、東京都では1996年に女性の転入超過が始まり、それ以来、女性の転入超過が続いています。
特に20代前半の未婚女性が就職をきっかけに地方から東京へ移住し、その数は25年で90万人を超えました。
一方、地元に残る結婚対象の若い女性が少ない地域では、未婚化が進行し、少子化が深刻化しています。
天野さんは、
「人口減少に悩む地方では、大卒の女性を雇用できる職場を提供することが重要です。自治体は地元企業に対し、『女性の雇用が進まなければ転出が増え、子どもが減少する』と強調する必要があります。地元経営者に対しては、中長期的な視野で雇用を創出してほしいとお願いすることしか方法がありません」
と指摘しています。
地元を愛している若者、でもなぜ地方を離れる?
天野さんは、いくつかの自治体で人口問題に関する専門的な助言を行っています。
人口減少に悩む地域の現状に寄り添いながら、彼は強い思いを抱いています。
「今の若い人たちは、自分の地元を批判することはありません。彼らは自分が生まれ育った場所が好きで、育ててくれた親や祖父母を尊敬しています。そして、故郷を愛していることを誇りに思いながら、それでも学校を卒業すると東京に出て行くのです。どうしてだと思いますか?それは、自分が幸せになるための選択だからです。地元という『船』は、今の若者が目指す理想の場所には向かっていないからこそ、彼らは故郷を離れるのです。」
地方からの「いつか帰ってきて」という呼びかけは、東京に出た若者には届かないのが現実です。
地元を愛しているはずの若者が、なぜ去っていくのか。それを考えることが、少子化対策の第一歩であると天野さんは指摘しています。