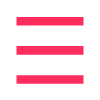東京都内で暮らす30代前半の会社員・あおさん(仮名)は、昨年、精子提供を受けて子どもを授かった女性同士のカップル数組と、その子どもたちと出会う機会がありました。
「見た目はごく普通の人たちが、自然な形で子育てをしているんだな」そのとき初めて、目の前に存在する多様なかたちの「家族」を実感したといいます。
家族にも様々な形があります。今や同性であっても堂々とプロポーズできる時代。その先の「子どもが欲しい」という希望も叶えられる時代になりました。
(※2025年3月3日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
目次
自分たちらしい家族を目指して。心にしまった願いと向き合う決意
あおさんは、生まれたときの性別は女性で、兄弟姉妹の多いにぎやかな家庭で育ちました。
幼いころから子どもを持ちたいという願いはありましたが、中学生のころに女性を好きだと自覚してからは、その思いを心の奥にしまい込んでいたといいます。
しかし30代に入り、将来について真剣に考える中で、長い間ふたをしていた気持ちと改めて向き合うようになりました。
現在の女性のパートナーとは交際を始めてから11年が経ち、すでに一緒に暮らしていたため、子どもとともに過ごす家庭の姿が少しずつ具体的に思い描けるようになったのです。
パートナーも、同じように子どもを望んでいました。
あおさんは血縁に強くこだわっていたわけではなく、当初は里親として子どもを迎える道も検討しました。
しかし、養育里親は一定の期間だけ子どもを預かる制度であり、同性カップルが法的な親子になるための特別養子縁組は、現行の法律では認められていません。
そのため、現在は海外の精子バンクを通じた妊娠を目指し、昨年末からパートナーが日本国内の医療機関に通院を始めています。
ありのままの家族で生きる。変わりゆく社会への願い
社会に対する不安は少なからずあります。
これまで、自分の性自認や女性のパートナーがいることについては、家族や友人、職場の誰にも打ち明けることなく過ごしてきました。
誰かに話すとき、事実とは異なる話を作らなければならない苦しさを、あおさんは身をもって体験してきました。
そして、自分たちの家族のかたちが一般的な枠から外れていることで、子どもにも似たような重荷を背負わせてしまうのではないかと心配しています。
それでも、「そのときには、社会が今よりももう少し寛容であってほしい」と、希望を込めて語ります。
2人の愛が3人に広がる、選んだ命と歩む新たな日々
東京都内で暮らす30代の女性も、海外の精子バンクを利用し、日本の医療機関で生殖補助医療を受けました。
今年2月、同性のパートナーが立ち会う中、元気な男の子を出産しました。赤ちゃんの産声を耳にした瞬間、2人の目には自然と涙があふれたそうです。
本格的に子どもを迎えることを意識し始めたのは、約2年前のことでした。
それまでに、親しい女性カップルの友人たちが次々と出産し、その姿を見て「自分たちにもこうした選択肢がある」と実感するようになったのです。
「2人でいても十分幸せ。でも、子どもが加われば、その幸せがさらに大きくなる気がしました」と語ります。
そして今、約10年にわたり共に暮らしてきたパートナーと、生まれたばかりの赤ちゃんとともに、3人での新しい暮らしが始まっています。
気になる生殖補助医療の行方、法律婚に限られる制度に広がる懸念
2024年9月上旬、一般社団法人「こどまっぷ」が主催するオンライン講座には、子どもを望む約40組の女性カップルなどが参加しました。
参加者たちは、子育てに向けた心構えや、子どもに出自を伝える大切さ、そして法的な親子関係の在り方について学んでいました。
そんな中、子どもを持ちたいと願う女性カップルにとって、大きな懸念となっているのが、現在国会に提出されている「特定生殖補助医療法案」です。
この法案は、自民党・公明党・日本維新の会・国民民主党の4党によって提出されたもので、体外受精や人工授精などの不妊治療に関するルールを定めようとするものです。
中でも、第三者から精子や卵子の提供を受けて出産に至った場合、子どもが自らの出自を知る権利を保障するという点は重要な内容です。
しかしながら、法案ではこの医療行為の対象を「法律上の夫婦」に限定しているため、もしこのまま成立すれば、同性カップルや独身女性、あるいは法律婚をしていない事実婚のカップルが、医療機関で提供精子や卵子を使った治療を受けることが事実上違法となってしまいます。
このような制限が施行されれば、安全で正規の方法による妊娠の道が閉ざされ、リスクの高い手段に頼らざるを得なくなる可能性もあり、当事者たちからは不安の声が上がっています。
安全な医療を奪わないで・・・生まれくる子どもの未来を守る
もし医療機関での生殖補助医療が受けられなくなれば、個人同士での精子提供に頼らざるを得ない状況に追い込まれます。
病院を介さない方法では、感染症のリスクが高まるほか、精子提供者がカップルの意思に反して法的な父子関係を主張するなどのトラブルも起こり得ます。
「SNSなどを通じてしか精子提供を受けられなくなる」という現実に、当事者からは強い不安と反対の声が上がっています。
一般社団法人「こどまっぷ」の代表である長村さと子さん(41)も、同性パートナーとともに、精子提供によって授かった3歳の子どもを育てています。
「この子には、どうしても生まれてきてほしかったんです。でも、もし法律が成立してしまえば、『違法な方法で生まれた子』と見なされる可能性がある。それはすでに生まれている子どもたちの権利を否定するようなものです」
と、胸の内を語っています。